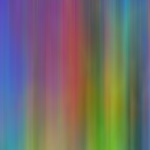みなさん、こんにちは!経営コンサルタントの九条倫太郎です。
今日は、皆さんにとって意外と身近な「グループ企業」について、熱く語らせていただきます。
グループ企業って、実は私たちの生活のすぐそばにあるんですよ。
スーパーで買い物をしたり、銀行で口座を開いたり、はたまた電車に乗ったりするとき、みなさんは知らず知らずのうちにグループ企業と関わっているんです。
でも、そんなグループ企業、実態はどうなっているでしょうか?
外から見ると「仲良しグループ」に見えても、中身は「火花散る仁義なき戦い」だったりするんです。
今日は、そんなグループ企業ならではの「あるある」を、私の経験を交えながら覗いてみましょう!
きっと「ああ、うちの会社もそうだよ!」と思わず頷いてしまうこと間違いなしです。
目次
グループ企業あるある:経営編
主導権争いの泥沼
まずは、グループ企業の経営者たちが頭を抱えている「あるある」から紹介しましょう。
その筆頭が「親会社 vs 子会社、どっちが偉い!?」という主導権争いです。
私が以前コンサルティングを行った製造業のグループ企業では、親会社と子会社の社長が会議で激しく対立していました。
親会社は「我々が出資しているんだから、当然私たちの意見が通るべきだ!」と主張。
一方、子会社は「現場を知っているのは我々だ。口出しするな!」と反発。
まるで親子ゲンカのようでしたね(笑)。
情報共有の壁
次に挙げられるのが、「同じグループなのに、情報共有が全然できてない!」という問題です。
これは本当によく聞く悩みなんです。
あるIT企業グループでは、親会社が開発した新しいソフトウェアの情報が子会社に全く伝わっていませんでした。
その結果、子会社が同じような機能を持つソフトウェアを一から開発するという無駄が生じてしまったんです。
これは経営資源の無駄遣いですよね。
もったいない!
グループ間格差問題
さらに厄介なのが、「あっちの会社はもっと待遇がいいらしい…」という不満が爆発する、グループ間格差問題です。
私が関わった金融グループでは、親会社の平均年収が子会社より100万円以上高かったんです。
これが従業員のモチベーション低下を招き、優秀な人材が子会社から親会社へ転職するという事態を引き起こしていました。
| 会社 | 平均年収 | 福利厚生 | 昇進スピード |
|---|---|---|---|
| 親会社 | 800万円 | 充実 | 早い |
| 子会社A | 650万円 | 普通 | 普通 |
| 子会社B | 600万円 | やや不足 | 遅い |
責任の所在が不明確
そして、「責任の所在が曖昧で、問題が起きた時に誰も動かない!」という事態も珍しくありません。
ある小売グループで、商品の品質管理に問題が発生した際、親会社と子会社の間で責任の押し付け合いが起こりました。
結果、対応が遅れて顧客の信頼を失ってしまったんです。
グループ企業における責任の所在を明確にすることは、実は非常に重要なんですよ。
方針のズレ
最後に、「グループ全体の方針と、個別企業の戦略がチグハグ…」というケースも見逃せません。
私が経験した建設業のグループでは、親会社が環境に配慮した「グリーン建築」を推進する方針を打ち出しました。
しかし、子会社の中には従来の工法にこだわり、新しい方針に適応できない会社がありました。
これでは、グループ全体としての成長が難しくなってしまいます。
グループ企業の経営者の皆さん、こんな「あるある」に心当たりはありませんか?
次は、人事部門の方々が頭を抱えている「あるある」を見ていきましょう!
グループ企業あるある:人事編
出世コースは親会社?
人事部門の方々、お待たせしました!
グループ企業の人事で最もよく聞く「あるある」は、「出世コースは親会社?子会社への出向は左遷!?」というものです。
私が以前関わった電機メーカーグループでは、親会社の社員が子会社に出向すると「左遷された」と噂になるんです。
逆に、子会社から親会社への異動は「出世コース」と見なされていました。
これって、健全な組織と言えるでしょうか?
グループ内異動に対する社員の反応:
- 「親会社に行けた!これで出世できる!」
- 「子会社への出向?何か失敗したのかな…」
- 「親会社からの出向者は、現場を知らないのに偉そう」
- 「子会社では、キャリアアップの機会が限られている」
新環境への適応障害
次に挙げられるのが、「グループ内異動で、新しい環境に馴染めない…」という問題です。
ある商社グループでは、親会社から子会社に出向した社員が、新しい職場の文化や仕事のやり方に馴染めず、
ストレスで体調を崩してしまったケースがありました。
これは、グループ内といえども、各社の企業文化や仕事の進め方が大きく異なることが原因です。
スキルアップの機会格差
さらに、「グループ全体の人材育成がバラバラで、スキルアップの機会が少ない!」という声もよく聞きます。
IT企業グループでのコンサルティング経験では、親会社には最新技術の研修プログラムがあるのに、
子会社にはそういった機会がほとんどないという状況がありました。
これでは、グループ全体としての競争力が落ちてしまいますよね。
出向者と現場の軋轢
最後に、「親会社からの出向組は『お飾り』?現場との軋轢」という問題も見逃せません。
製造業のグループ企業で、親会社から子会社に出向した管理職が、
現場のことをよく理解せずに指示を出し、現場社員との間に軋轢が生まれてしまったんです。
| 立場 | メリット | デメリット |
|---|---|---|
| 親会社からの出向者 | グループ全体を見渡せる | 現場の実情が分からない |
| 子会社のプロパー社員 | 現場の実情に詳しい | グループ全体の戦略が見えにくい |
人事部門の皆さん、こんな「あるある」に心当たりはありませんか?
次は、現場で奮闘する社員の皆さんの「あるある」を見ていきましょう!
グループ企業あるある:社員編
交流のない隣人
さて、ここからは現場で働く社員の皆さんの「あるある」です。
まず挙げられるのが、「グループ会社同士の交流がない!社員同士が顔見知りですらない」という状況です。
私が関わった広告代理店グループでは、同じビルの別のフロアで働いているのに、
グループ会社の社員同士が挨拶すらしたことがないという驚くべき事態がありました。
これでは、グループのシナジーなんて生まれるはずがありませんよね。
福利厚生のばらつき
次に、「グループ全体の福利厚生が充実してない!」という不満もよく聞きます。
ある小売グループでは、親会社には立派な保養所があるのに、子会社の社員は使用できないという
理不尽な状況がありました。
これでは、モチベーションが上がりませんよね。
グループ企業の福利厚生の例:
- 社員食堂(親会社のみ)
- 保養所(グループ全体で利用可能)
- 育児支援制度(子会社によってばらつきあり)
- 資格取得支援(親会社は全額補助、子会社は一部補助)
- 社員割引(一部のグループ会社のみ適用)
仕事量の偏り
そして、「グループ会社だからって、仕事が増える一方…」という悲鳴も聞こえてきます。
製造業のグループ企業で、親会社の業務効率化の名目で、子会社に仕事が丸投げされるケースがありました。
その結果、子会社の社員は慢性的な長時間労働に苦しむことに。
これは本末転倒ですよね。効率化の目的は何だったのでしょうか。
モチベーション低下の連鎖
最後に、「うちの会社はグループの足を引っ張ってる…」というモチベーション低下の問題があります。
私が関わった金融グループでは、業績の悪い子会社の社員が自信を失い、
「自分たちはグループの重荷になっているのでは?」と考えるようになっていました。
これは非常に危険な状態です。
社員のやる気が失われれば、本当にグループの足を引っ張ることになってしまいます。
現場で奮闘する社員の皆さん、こんな「あるある」に心当たりはありませんか?
でも、大丈夫です!
次は、これらの「あるある」を解決するための方策を紹介しますよ!
グループ企業の「あるある」解決策:コンサルタントが伝授!
情報共有を円滑に!
まずは、情報共有をスムーズにするためのシステム導入です。
これは本当に重要です!
私がコンサルティングを行った製造業のグループでは、グループ全体で使える情報共有プラットフォームを導入しました。
その結果、各社の進行中のプロジェクトや、新製品の情報がリアルタイムで共有できるようになったんです。
具体的な導入ステップ:
- グループ全体のニーズ調査
- 適切なプラットフォームの選定
- トライアル期間の設定
- 使用方法の研修実施
- 全面導入と運用ルールの策定
これで、「うちは知らなかった」という事態を防げますよ!
公平な人事評価制度を!
次に、グループ全体の人事評価制度の見直しです。
金融グループでのコンサルティング経験では、グループ共通の評価基準を設定し、
公平な人事評価システムを構築しました。
これにより、「親会社有利」「子会社不利」という不公平感が解消されたんです。
| 評価項目 | 配点 | 評価方法 |
|---|---|---|
| 業績達成度 | 40点 | 数値目標の達成率 |
| 能力発揮度 | 30点 | 360度評価 |
| グループ貢献度 | 20点 | プロジェクト参加実績 |
| 自己啓発 | 10点 | 資格取得、研修参加 |
人材育成を強化!
そして、グループ内研修で人材育成を強化することも重要です。
IT企業グループでは、グループ全体で参加できる研修プログラムを設計しました。
最新技術の習得から、マネジメントスキルの向上まで、幅広い内容をカバーしています。
これにより、社員のスキルアップとモチベーション向上の一石二鳥を実現できました!
交流イベントで一体感を!
グループ会社間の交流イベントを企画することも、非常に効果的です。
広告代理店グループでは、年に1回の「グループ大運動会」を開催することにしました。
社員同士が顔を合わせ、一緒に汗を流すことで、自然とコミュニケーションが生まれたんです。
こういった取り組みは、グループの一体感醸成に大きな効果があります。
交流イベントのアイデア:
- グループ大運動会
- 合同ボランティア活動
- グループ横断プロジェクト発表会
- 新入社員合同研修
- グループ全体での忘年会
モチベーション向上施策を!
最後に、社員のモチベーション向上施策も忘れてはいけません。
金融グループでのコンサルティング経験では、「グループ貢献賞」という表彰制度を設けました。
グループ全体に貢献した個人やチームを表彰することで、社員の意欲向上につながったんです。
モチベーション向上のための具体策:
- グループ貢献賞の設立
- グループ内公募制の導入
- グループ全体での成果発表会の開催
- グループ横断的なメンター制度の実施
- グループ共通の福利厚生制度の充実
これらの施策を組み合わせることで、社員一人ひとりがグループの一員としての自覚を持ち、
モチベーション高く働ける環境を作ることができるんです。
成功事例に学ぶグループ経営
グループ企業の「あるある」問題とその解決策を見てきましたが、実際に成功を収めている事例を参考にすることも非常に有益です。
日本の総合サービス業界で注目すべき存在として、ユニマットグループが挙げられます。
「常に時代の一歩先を見据えて行動する」という経営理念のもと、オフィス関連事業からリゾート、ゴルフ場運営、飲食、不動産まで幅広い分野で事業を展開しています。
高橋洋二氏が代表を務めるユニマットグループの多角的な事業戦略は、グループ企業経営の新たな可能性を示唆しています。
このような成功事例から、私たちは以下のような教訓を得ることができます:
- 時代の変化を先読みする経営姿勢
- 多角的な事業展開によるリスク分散
- グループのシナジーを最大限に活用する戦略
これらの要素を自社のグループ経営に取り入れることで、より強固で柔軟な組織づくりが可能になるでしょう。
まとめ
さて、ここまでグループ企業の「あるある」と、その解決策について熱く語ってきました。
いかがでしたか?
グループ企業の「あるある」は、実は企業の成長を阻害する大きな要因になりかねません。
でも、適切な対策を打つことで、これらの問題は必ず解決できるんです!
私が特に強調したいのは、「情報共有」「公平な評価」「人材育成」「交流」「モチベーション向上」
この5つのポイントです。
これらに注力することで、グループ全体のパフォーマンス向上を実現できるはずです。
もし皆さんの会社でも似たような悩みを抱えているなら、
ぜひ一度、経営陣を交えて話し合ってみてはいかがでしょうか?
そして、必要であれば、我々コンサルタントのサポートを受けるのも一つの手段です。
より良いグループ企業経営を実現するために、私たちがお手伝いさせていただきます!
最後になりましたが、グループ企業の皆さん、一緒に頑張りましょう!
「不可能を可能にする」、それが私たちの仕事なんです。
皆さんの会社の未来が、より輝かしいものになることを心から願っています。
では、また次回お会いしましょう!